『ワークスアプリケーションズ創業者牧野正幸氏スペシャル対談』 Part2.そもそもDXとは?しがらみからの脱却と勇気あるX-formationの追求
2022年3月1日
株式会社パトスロゴス 代表取締役CEO
牧野 正幸(まきの まさゆき)
日本IBM契約コンサルタントを経て、1996年ワークスアプリケーションズを創業。COMPANYシリーズのグランドデザインを固め、日本初の大企業向けERPを開発販売。
数多くの上場、未上場の企業の経営アドバイスを行い、CEO退任以降は同様に経営アドバイザーとして活躍。2020年10月、日本におけるデジタルシフトの遅れを取り返すことを目的に株式会社パトスロゴスを創業。DXに寄与する自社製品の研究開発とサービスを提供すると共に、ベンチャー企業への経営支援、優秀なビジネスパーソンの輩出のサポートをしている。
株式会社InfoDeliver監査役
桐原 保法(きりはら やすのり)
ソニーで長年人事分野に従事、人事制度の変革や人事の国際化を進め、80年代には日本語ワープロの導入、オフィスコンピュータの導入等、OA化のリーダーを務める。2003年COMPANY導入をきっかけに、牧野氏と知り合う。人事や総務・環境・生産戦略等の役員を歴任し、退任後、ソニー健康保険組合理事長、ソニー教育財団副理事長などを経て、(株)InfoDeliver監査役に就任、現在は、ビジネスマンのコーチとして20名ほどのコーチも務めている。
MC:そもそも、DXとは何なのでしょうか。バズワードという言葉も出ていましたが、DXという言葉が新聞に載らない日はありません。今回はお二人が考えられるDXについてお話しいただけますでしょうか。
桐原:どっちから行きますか。まさに素人からいきましょうかね。ええと・・・そうですね。まさに、牧野さんがおっしゃっている、バズワードっていう風に私も捉えていて、やっぱり基本的にビジネスの世界、あるいは人間世界はトランスフォーメーションの積み重ね、繰り返しじゃないですか。
牧野氏:そうですね。
桐原:ある方向で切り口を変えたら、今度は違う方向から変えていくと、いろんなシステムの、あるいはフォーマットの変革の歴史と似ているなという気がしていて。ソニーの場合はそれこそレコードに対してCDを出して、MDを出して、その後半導体になって・・・というように、いろんな成功したものをどうやって壊すか、そういうことの繰り返しみたいな気がするんですよね。
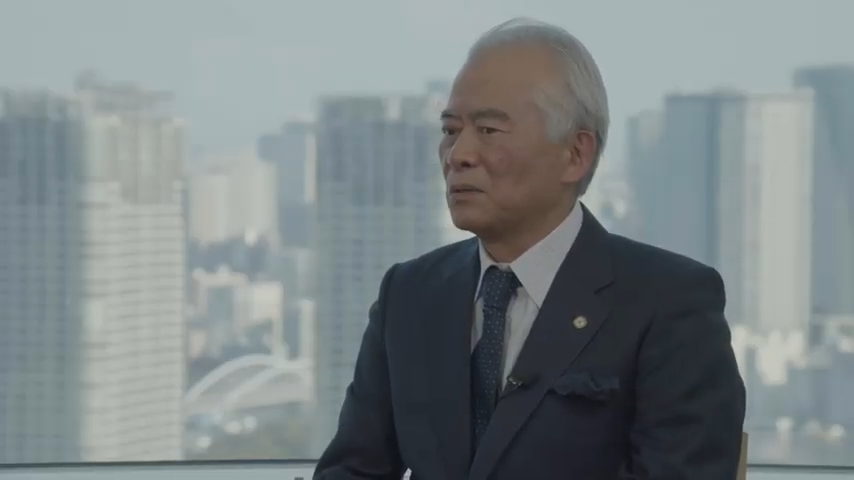
そのスピードがどんどんどんどん速くなってるんだけれども、同じようにITの世界だって成功したら今度は違うものが生まれてくる、そういうことをどんどんどんどんやっていかないとやっぱりダメだよねってことを、みんながなかなか認識できずに一生懸命毎日のことをやっていたんだけれど、そこにアメリカ、ヨーロッパ、中国あたりでいろいろな、その新しい動きが生まれてきている。
世の中をちゃんと見るというゆとりがなくなっていることによって、デジタルトランスフォーメーションに遅れをとってしまっている日本、そんな気がするんですけど。一番ご存じの牧野さんに、その辺を教えて頂きたいなと思っているんですけど。
牧野氏:日本のデジタルトランスフォーメーションが遅れている…まぁ、あえて遅れているという意味でいうと、そもそも日本の企業というのは、今回のデジタルトランスフォーメーションの一番大きなポイントは、デジタルの技術を使うことによって、世の中に大きな変革を与えましょうということ。一番の事例でいうとGAFAMと言われている人たち、特にその中でも大きかったのはやはりNetflixだとかAmazonは、実際の皆さんの生活の中でも大きく世の中に変革を与えた。特に小売という意味でいうとAmazonはとてつもなく大きな、実際ウォルマートに匹敵する。アメリカのウォルマートというのはずっと無敵でしたけれど、(今もまだまだすばらしい会社ですが)それをかなり追い込むところまで来ている。日本においても同様なことが起こっているということで、ここはもう完全にそういう意味ではデジタルの世界に変わっていっていると。

私は、ソニーはかなり早くにデジタルトランスフォーメーションやっていたなと思っていて。賛否ありますけれど、私はどっちかというと賛の方ですけど、それまでのソニーというのは僕らの中ではAVのソニーですから、オーディオビジュアルで、要はハードウェア、素晴らしいハードウェアを作る会社というイメージだったのが、あるタイミングからエンターテインメントだとか、ゲームだとかインターネットだとか、もうどんどんそっちの方向に、むしろ急激に一番まだ(業績が)そんなに悪くない時期に大幅にシフトしたじゃないですか。でも結果的に今はそれのおかげでソニーってすごい収益のレベルの高い、総合家電メーカーだった中で言ったら唯一独り勝ち状態だと僕は思うんですよ。
そういう意味ではもう、まさにあれがトランスフォーメーションの究極だなと思うんですがその辺はどうですか。
桐原:それこそ私はちょうど2000年前後に、ソニーの製品の修理を請け負う「ソニーサービス」という会社の社長をやってたんですね。その頃にソニーサービスの収益の一番のポイントはまだ回転式のテープレコーダーだったんですよ。それを一台修理すると1万円もらえるような時代だったんですね。ところがそれがその頃急激に減り始めたんです。ということは従来のエンジニアがどんどんいらなくなってくるんですよ。その代わりに新しくデジタルの商品が、もちろんそれ以前から売られ始めていたんだけれど、どんどん置き換わり始めていて、まさにアナログからデジタルへ変換が進んでいる頃だったんですね。で、その頃に出井社長がまさにデジタルドリームキッズだといって、将来は世界が変わるぞと、このまま延長線ってことはあり得ないってことを言って、もちろん既存のビジネスをやっている人たちも当然いっぱいいた訳ですから、この人たちとの間でいろんな意見のやりとりをして。
牧野氏:ありましたね。
桐原:すごく反発はありつつ、でも例えば20年先、30年先は必ず変わるね、ということに関してはみんな異論がなかったんですよ。そういう議論が20世紀の間に丁々発止できたことがやっぱり大きかった。
牧野氏:大きいですね。
桐原:というふうに思いますね。ついついみんなは守りに走りたがるときに、出井さんおよび周囲のメンバーたちは、「やっぱりこのままじゃダメだね」と、いうことを本当に感じ始めていたんだろうと思います。それが今に至るきっかけを作ったんだろうなと。
その一つ前がプレイステーションなんですよ。プレイステーションは90年代の初めですよね。エレクトロニクスの世界っていうのは売ってナンボなんですけど、プレイステーションは結局ハードウェアとソフトウェア二つあって、製品を売って、あと今度はソフトウェアで儲けるというようなビジネスのモデルになっていて、要はビジネスモデル一本じゃないな、ということをみんなが認識し始めたっていうのもひとつのきっかけになったのかもしれませんね。
牧野氏:私は、講演で、DXの話をするときに、勝手によくソニーさんの話をしていて、
デジタルということをちょっと置いてでも、トランスフォーメーションというのはああいうことをトランスフォーメーションと呼ぶんですよと。結局それまでのソニーのイメージがあって、だから結構ネットなどには、「やっぱり昔のソニーも良かった」、「あんなに素晴らしいカメラとか、テレビを作っていたのに、今のソニーはそういうのはまったくやらなくなっちゃって、もう全然ダメだ」みたいに言う人もいるんですが、こういう人ってもう時代から遅れていっちゃっている人なんですよ。
もちろんそれは、年間二百万円でも使い続けてくれる人が何十万人もいるんだったら、それが成り立つけれども、成り立たないでしょ、という。だからそういう意味でああいうトランスフォーメーションを行えばものすごいコンフリクトが社内にあったんじゃないですか。
実際僕も社内のことはわからないですけども、外から見ていたらいろいろなところで一時期出井さんが世界最高峰の経営者と言われたのが、最低の経営者まで言われるまで、もういろいろな人がいろいろなことを言うわけですよ。

すなわちトランスフォーメーションをするというのは、そういうことなんですよね。で、それは直ちに成功するなら誰だってやるんですけど、やはりあれだけの規模の企業や今日本でトランスフォーメーションをしなければならないと言われているような大企業、すなわち一流企業ほど過去の成功してきたものと、過去積んできた資産がいっぱいある、これが場合によっては負の遺産になっちゃうケースもあって、これを全部破壊せざるを得なくなると、これはもう袋叩きになるに決まってますよね。
桐原:ほんと、ほんと。
だから本当に勇気をもった発言だったと思う。
牧野氏:そうなんですよね。
桐原:方向転換だったと思うし、当然本当に大きな議論も巻き起こったんですよ。混乱も起きました。
牧野氏:ですよね。
桐原:だけどやっぱり、ここでやっぱり共通の目標をあの人は提示してくれたのは、それはすごく良かったです。
牧野氏:そうなんですね。
桐原:足元はいろいろあるけれど、先はこっちだねという意識がみんな持っていると、やっぱりどっかで動いていきますからね。そういう何か・・・。
やっぱり経営っていうのはもちろん足元も大事だけど、先を見た方向、方向付けっていうのはすごく大事かなと。

牧野氏:ですよね
桐原:と、思いますね。
牧野氏:なので、今のお話が私の中では、最も唯一の、と言ってもいいぐらいの日本の一流企業のトランスフォーメーションの事例だと思うんですよ。実際アメリカにはトランスフォーメーションが起こりやすいと言いますけれども、実際にはトランスレーションがどれだけ起こっているかというと、日本の5倍ぐらいは起こってます。
本来イメージしているものでいうと、実はトランスフォーメーションを起こしているのはほとんどベンチャー企業なんですよ。ただ言ったらトランスも、社会的なトランスフォーメーションを起こしますけれども、企業としては最初からもう何も持っていない状況だからできるというのがあって、それが世の中に出てきている。だからAmazonだって別にもともと小売業だった訳でも何でもないですから、いきなり出てきて、今のポジションになったわけで、決して元々アメリカで有力だった本屋がそれをやったわけじゃないんですよ。
だからアメリカでも進んでいるエリアというと、トランスフォーメーションされているのは確かですけれども、日本よりもはるかに多いです。ただ日本より多い理由はもうたった一つで、アメリカのCEOは3年で結果出さないとだいたいもうダメなんですよね。ということは3年の間に何かをやり遂げないとダメなので、逆にいったら、3年間そこそこの成果だったら外されちゃうわけですから、大きな成果を出さないとしょうがないんで、失敗覚悟でやることができる。ただ日本のCEOはそうじゃないじゃないですか。要はいろんな人の引きもあって、上がっていっていて、なおかつCEOになってからもそれなりの期間、やる場合もありますし、逆に言うと成果を出してもそんなに長くないケースもあれば、成果を出さなくても長いケースもあれば、これはもう本当にアメリカ型のいわゆるCEOというのはもうどっちかというと雇われですから、完全に。下から上っていたわけではないので。

桐原:そうそうそう。結構やっぱり、よそから来る人が多いんですよね。まさに違う視点を入れるし、何か一種の会社全体を変えていくにはやっぱり違う視点がすごく大事。
牧野氏:大事です。
桐原:ことですよね。
牧野氏:だと思います。
桐原:日本でもいろんな意味で、経営層のヘッドハンティングというのは随分増えてきていて、そういう人たちがやっぱり会社を変えようと、努力しているというのがすごく大変だと思いますけども、でも日本もそうやって変わっていくんだなということを今感じるんですね。そういう意味で今ソニーのお話がありましたけども、実はごく最近日立の話も聞いたんですが、あちらも本当のビジネスフィールドがものすごく変わりましたね。東芝だって苦労し
ながら、今3分割の話とか出てるじゃないですか。いろんな意味で今までの延長線ではやっぱりやっていけないっていうことが、エレクトロニクスの世界には本当に浸透し始めている。し始めてる、しちゃっていると言った方が良いですよね。ということはもう事実だと思うので、あとはいつどうするか、という話なんだろうと思います。振り返ってみるとやっぱり日本の電機業界は、わーっと世界に売れ、特にアメリカあたりではもうどんどんダメになる会社が続出したんですね。
牧野氏:いっぱいありましたね。
桐原:ヨーロッパでもそうですね。
牧野氏:そうですね。
桐原:だからそうやって企業というのは、こう、まさに倒し倒されていくようなそういう歴史を繰り返しているじゃないですか。だからそんな中でなんだかんだ言いながら自らトランスフォームしているから生き残っているわけで。だからやっぱり自らをまさに自己否定するってことがすごく大事なことを感じるんですよね。
牧野氏:なので、日本でトランスフォーメーションが進まない一番の理由というのは、CEOにメリットがないからだと思います。まあ、一言でいうと。やはりそのメリットがないというのはそこまでもちろん個人のことをCEOになる人は考えているわけじゃないんですけれど、やっぱりやりきれない、やった時のネガティブファクター、尚且つトランスフォーメーションすると確率的には、まあ良くて7:3で3は相当なダメージを受けることになりかねないんですよね。
それを今利益が出ている会社ができるかというと、それはなかなかできないんですよ。だから実際これが結果どうなるかわかりませんけど、日産さんなんかは結局やっぱり業績が悪かったんで、そこにルノーとの提携があって、外国人の経営者の方が来てドカンと全部変えたじゃないですか。今までのままに行ったら潰れるんだからっていう、もうすごく強い力を持っていた訳ですよね。おそらく今シャープさんもそうやってどんどん変わっていると思うんですよ。だからこれは一番やりやすいパターンだと思います。ただ、業績や実は悪い会社はともかく、日本の一流企業の大半は業績が良いわけですから、そうすると業績がいいのにもかかわらずトランスフォーメーションするとなると、これはもう勇気のレベルじゃないぐらい勇気がいる話なんで・・・。

桐原:そういう意味で、長い間、仲間付き合いを続けながら社内で育ってきた人間にはなかなかできないですよね。
牧野氏:できないと思うんですね。
桐原:仲間を切らなきゃいけないからね。
牧野氏:そうなんですよね。だから海外の場合で、トランスフォーメーションがうまくいっているのは、CEOはもともとそれをやれということで入ってきているので、絶えずトランスフォーメーションしようとしていて、今回のデジタルのツールを使えばもっとトランスフォーメーションできるだろうということで、デジタルトランスフォーメーションが僕は進んでいると思います。
一方で中小企業といいますか、スモールビジネスの領域は、先ほど申し上げたようにゼロから作るベンチャーもあれば、そういうツール群を使って簡単にトランスフォーメーションできる領域というのもあるんですね。特に今回でいえば、世の中がコロナもあって、テレワークになってとか様々な流れの中でいろいろなことが実は変わってきています。特に飲食店は、相当技術革新が入っているんですよね。例えば飲食店のメニューがなくなっていて、メニュー置いてない店はいっぱいあるじゃないですか。
コロナなので、スマートフォンでQRコードを読みこんでメニューを見てくれって。そういう風に変わってきていますし、あと一生懸命彼らも顧客の獲得をしなきゃならないので、ネットでの予約をするのが当たり前、あとデリバリーもネットで予約して、今Uberだとか出前館などいろいろありますけど、ああいうのももう完全デジタル化されているので不思議な世界がいっぱい生まれたじゃないですか。このコロナの間で。私が見ていて思うのが、赤坂ですね。あるエリアに行ったら、自転車が20台ぐらい止まっているんですよ。そこにずっとスマホを触っている人がいるんですよね。オーダーがきたら速攻にそこから飛んで行くために。あそこはちょうどいっぱいお店があるんで、お店に取りに行って、それでまた行くという。
あのシステム、裏側はすごくよくできたシステムになっていて、お店にも簡単で、そんなに複雑なシステムもいらない。お店に置いてあるのもiPadぐらいで、それで全部の仕組みができちゃう。こういうことで実は飲食業でも自分たちの力や、もしくはそういったツール群を使うことによって、どんどんデジタルトランスフォーメーションが起こっています。
なので、今一番その日本で危惧をしなければならないのは、日本を支えてきている、そして今も支えている一流企業が、どうデジタルトランスフォーメーションできるかということが大きなポイントなんです。ただ先ほど申し上げあげたように、あまりにもリスクが大きすぎるし、やりきれないということもあって、業績のいい会社がやるのはちょっと難しい。私は実はそれに関しては2つ方法があると思っています。これはわりと多くの会社が既にやっていることですけれども、ひとつはまずDXに即したような、子会社を作って,
そこはもう全部任せきる。全く新しいことを勝手にやってくださいよ、という風にやると、これがひとつの大きなデジタルトランスフォーメーションになると思います。
まさにソニーもSony Computer Entertainmentがそうだったと思いますが。
桐原:あの時は本当にファイヤーウォールを作りましたからね。当時の大賀会長が、もう絶対触るなと、これはもうやらせるんだと言って。あれは本当に見事な指示を出されましたよね。
牧野氏:やっぱりそこが完全に分かれた会社であったので、グループの中とはいっても。自在にできたと思うんです。
実際ゲームの業界でいうと任天堂さんが先行して成功していましたから、恐らくそこからのゲーム業界であったらこうするんだ、というものを取り入れながら、いわゆるデジタルトランスフォーメーションではないですけれども、トランスフォーメーションをかけたんだと思います。完全に。
桐原:はい、そうです。
牧野氏:それが1つの方法で、それをやることによって、もう関与しない、もっと言ったら助けてもあげないぐらいの。要はもう、助けると結局どんどんどんどん血が入っていっちゃうので、もう助けないし勝手にやってくれというので、人材は十分にいますし、資本力もあるので、そういうことが多分できるんじゃないかなと。
桐原:そうですね。だから本当に1、2年で1兆円のビジネスになりましたからね。あれは見事でしたね。
牧野氏:だと思います。
それが一つですね。あとまあ、もうひとつは大企業でトランスフォーメーションしようと思ったら、今のような形でまったく新しいビジネスを、もしくは自社と同じビジネスをトランスフォーメーションした形でやってみろという子会社を作るといい思うんですよ。
要は、場合によっては競合相手になりかねないようなものだけど、生み出すことによって、自分で自分を破壊するのが一番だと思うので。それが一つ。単純なこう何か関係ないインターネット子会社でも作っておけじゃなく、自社の商品と競合するようなものを作ってやらせる。これが一つだと思います。
場合によってはこれがすごく大きくなれば、それに取って代わる可能性ももちろん出てくるわけですから。もうひとつは実はこれはちょっと、そこまでやりきれないという、もしくはデジタルそのものの革命があまり直接的に自社の業績に影響しないタイプの会社もあるんです。まだデジタルの流れがそれほど来ない業種っていうのも実はあるのはある。そういった会社に対しては、方法論はもっとシンプルで、そもそもトランスフォーメーションをするときにみんなが怖がるのは、業績に直結するからなんですね。

例えば日本の企業って実はインターネットの時代に言われていたインターネット、実はロングテールなビジネスだってよく言われていたんですけど、要は普通だと取り扱わないようなものでもネット上だったら別に取り扱っていてもコストがかからないんで、って言うんですけど、実は大企業ほど、いわゆるロングテール型のビジネスをやっているのはないぐらい。日本の大企業というのはいろいろなところとの取引があるので、ほとんど年に1回しか売れないようなものでも、結構在庫を持っていたりする。そういったものをやめたときに相手との取引関係がどう悪化するかとか、競合相手にさらわれちゃうんじゃないかとか、いろいろなことが怖くて変えることができないんですよ。ところがトランスフォーメーションというのは本質的には企業のビジネスのあり方そのものを変えちゃうんで、そうすると今までの顧客の一部を失う代わりに、より多くの顧客を獲得すると必要性がある。ここは先ほども申し上げたように利益が十分出ている素晴らしい会社の場合、そこに手をつけるのは相当な勇気がいるんですよね。
桐原:いろんな意味の、まさにしがらみがありますからね。「しがらみがあってな…」と、いうともうそれは「変えない」ってことじゃないですか。
牧野氏:そうなんです。
桐原:だからトップとして大事なことは、しがらみがあっても変えるんだというそこの意志ですよね。その先の先はこうなるのだというのが見えていると、現状の問題は解決できるんだけど、それをあんまり意識していないとやっぱり今のままがいいなと、まさにデジタルトランスフォーメーションと言ったってな、ということになりますよね。そこの踏ん切りをどうするかなんでしょうかね。
牧野氏:そうですね。
なので、そういう会社が唯一デジタルトランスフォーメーションをやりやすい領域というのは、社内なんです。すなわち簡単にいうと人事、財務、総務、法務という領域って社内じゃないですか。これは社内の反乱作用を抑え込めれば、まったく革命を起こしても問題ないですね。なので、ここがやれない会社が、そもそもそんな、やはり顧客も巻き込んだことができるかというと、多分できないと思うんですよ。
例えばひとつの人事制度を1個取ってもそうなんですが、これはすべての企業グループで言えることですが日本の大企業で、給与と給与の手当てって何種類あるかというと、平均3000種類あるんですよ。
桐原:そんなにあるんですか。
牧野氏:あるんです。
桐原:システム的に分かれている訳ですね。
牧野氏:だから要はグループ会社も含めると、ちょっとずつ違うので、ものすごい種類があるんです。これ私たちもそうですが、ベンチャー企業だと2種類ぐらいしかないです。会社によっては。せいぜい2・3種類、多くて5種類なんですよ。それが何百種類もあるというのも、結局長い間のいろいろな問題と給与制度・人事制度を変えられない問題や、統合もできないし、もっといったら組合との関係もあるということで、なかなか変えられないままずっと残っているんですね。私はものすごい数の大企業の人事制度を見させていただいたので、その中で僕が一番衝撃を受けたのは、寒冷地手当っていうのがあるんですよ。この寒冷地手当って別に寒冷地なので5千円支給でいいじゃないですか。寒冷地手当の支給方法って灯油何リットル使うから、その灯油1リットルあたりいくらなので、いくら、という支払い方をしてる会社が今でも結構いっぱいあるんですよ。それを今の時代にする必要あります?そんなの手当として別に一律にその寒冷地だと言われるエリアには、1万円払いますでもいいわけですけど、何かその微妙な差をもう既得権益的に払っちゃっている限り下げたらダメみたいなのもあって、なかなかそれを変えられない。例えば、今、世の中はだいぶ変わりましたけれども精算、経費精算など、経費精算も実は冷静に考えたらとてつもなくおかしな、日本の企業の仕組みになっていて、あれはものすごい金額を会社が社員から借りている状態になっているんですよね。だけれどもこれはもうそれが当たり前になっているので変わらない。

あと笑い話ですけど、昔、交通費精算とかをやるときに、全部手書きで書いている会社がものすごい多かった、Excelとかが普及している時代にも絶えず手書きじゃないとダメってなっていたんですよ。なんで手書きじゃないとダメなんですかと言ったら、だってコピーしやすかったら不正するから。いやいやいやっていう。まあ分からない訳じゃないですけれどもそういう時代がずっと続いていたので、やはりそういうところというのは、全部変えることは可能だと思うんですよ。これは社内の問題ですから法的な問題を除けば軋轢を潰すことというのは少なくとも、ビジネスのあり方そのものを変えるよりは全然やりやすい領域だと思う。
桐原:そうですね。
牧野氏:まずはそこからやられたらいいんじゃないかなと私は思うんです。
桐原:おっしゃる通りですね。
私もそれこそまだ40なるかならない頃、社員番号を身分が変わると番号を変えてたんです。
で、海外に行くと違う番号、出向すると違う番号、それから管理職になると違う番号、だからライフタイムで四つか五つ番号を持つ可能性があった。ある時、システム担当の若いのがやってきて「もうかなわんのですと、とても大変なんです」と、僕に相談が来た。「わかった」といって、関係の課長さんたちに相談に行って、「何とかしてくれ」と。「変えないとこれはどうしようもないですよ、将来禍根を残します」と、言っても、説得するのにずいぶん苦労しました。でもわかってくれましたね。だからやっぱりそこを特に変え、いろいろな問題が見えてきたときにどうやって変えていくかというときには、やっぱり勇気っていうのはすごく大事なこと。結構みんな勇気がないので、どうやってみんなの勇気を出させるかっていうのが、大事なのかなと思いますね。今でもきっといろいろな人たち、若い人たちが悩んでいることはいっぱいあると思うんですよ。それをちょっと何か言うとだ文句言いやがって、蹴っ飛ばされることがきっと多いと思うので、そこのところをちゃんと吸い上げて生かしていけるような、そういう経営の仕方っていうのは、なんとかできるようになるといいなって、いつも思うんですよね。

牧野氏:そうですね。
今ちょうど勇気という言葉が出ていましたけど、デジタルトランスフォーメーションに限らず、そもそもビジネスプロセスエンジニアリングの頃からやっぱり、経営者の決断ですね。経営者だけじゃなく経営陣、あとマネージャー陣も含めて全体的に大体そういうのって変革すると言っても、現場担当者が反対するというケースがあまり多いわけじゃない。どちらかというとまあ、そういう方向性をきっちり決めてリスクも取るんだという覚悟があればできることではあると思いますけど。ただ日本の場合それをなかなか業績のいい会社はやりづらいというのがあるので、場合によっては、その場合は今申し上げたように、社内。社内だけで済むのであれば勇気は相当少なくて済むので…。それでも大変ですけどね。
桐原:大変ですけどね。
少なくともお客さんというのがないだけでも全然違います。
牧野氏:売上やお客さんとかに影響しないのであれば、まだかなりやりやすいので、それでも大変ですけれども、そこからやられたらいいんじゃないかなと。そこが確信できればそれによってどれだけこんなにコストメリットやコースメリットが出るかというのが分かれば、場合によってはそういう良い事例として、本当の本格的なトランスフォーメーションに入っていくこともできるんではないか、というのがあります。
桐原:一歩踏み出すということですかね。
牧野氏:だと思います。なのでデジタルトランスフォーメーションはデジタル、デジタル言いすぎなんですよ。そもそも日本というのもそうですし、世界的にそうですが、トランスフォーメーションが今、時代が変革する時には必要なんです。
桐原氏:必ずね。
牧野氏:だから機械から、いわゆるエレクトロニクスに行った時もそうですし、やはりビジネス的にいったら同じモデルじゃないじゃないですか。やはりいってもコモディティ化されるのが速い、エレクトロニクスの方が。で、ソフトウェアに関して言ったらもうコモディティ化されるのが速いどころか、もう部品そのものが存在しなくなっちゃったので。そういう意味でそこでトランスミッションがまた起こる。今回同じITの中でも旧来のITとその新しいITの間にものすごいトランスミッションが起こっちゃったので、ここをトランスミッションできない業界は、業界会社はダメだと思います。
なので、DX、DXと言っているあなたの会社こそDXって感じですね。あのITサービス業でいうと、まあそんなふうに思いますね。
桐原氏:なるほど。
聂 宏静(Nie Hongjing)
IngDanアカデミー編集長



